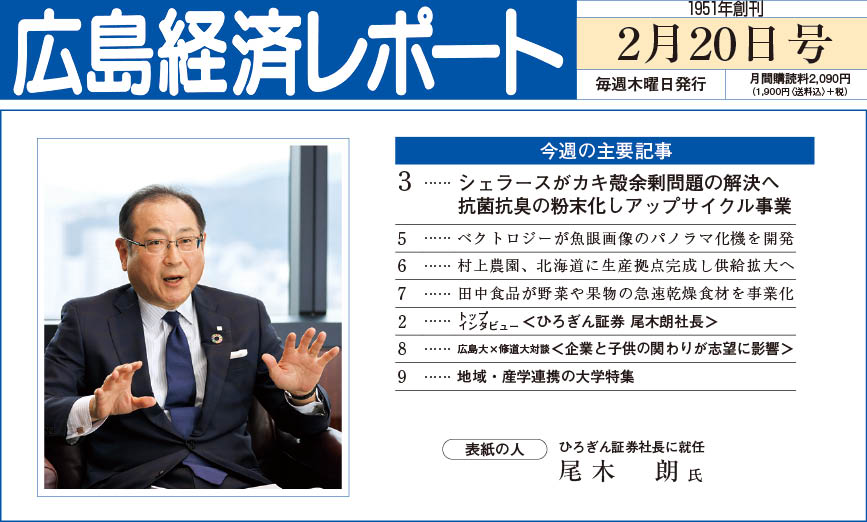

旬の材料を生かした和食に加え、10種類程度を用意する釜めしが売り。1月17日、流川から南区上東雲町5―6に移転オープンした。
「入居していたビルの老朽化などを受けて決断。席数が増え、ゆったり過ごしてもらえるようになりました。前の店の特徴だった、かがまないと入れない低い間口と丸形の窓枠は、あえて新店でもテーブル席で再現しています」
ランチには2000円前後の釜めし定食のほか、4800円の「うにの釜めし定食」なども。夜は野菜、魚介、肉といった多様なメニューをそろえ、ドリンクの種類もビールから日本酒、ワインなど幅広い。コース料理は6500円から対応し、釜めしの中身によって8500円などのプランもある。
「繁華街から離れてしまいましたが、変わらず来てくれる常連さんもいてありがたい。近所の人と話していると、この辺りは酒を飲める店が少なかったという声も聞いています。新しいお客さまとの出会いに期待。飲まない方には駐車場2台分も備えています」
繰り返す腹痛や下痢、長期化すると大腸がんのリスクも高まるといわれる。安倍首相も悩まされた潰瘍性大腸炎は根治の難しい難治性疾患の一つだが、光が差してきた。
広島大学名誉教授で、同大未病・予防医科学共創研究所長の杉山政則教授(74)は、
「植物乳酸菌の働きによって治る可能性が出てきた。今春を目途に、広島大学病院で医師主導の治験に入る。まずは機能性表示食品として申請し特定保健用食品を目指す」
2016年に広島大学薬学部長と薬学部教授を定年退任後も植物乳酸菌の研究を続けてきた。指定難病への挑戦はイチジクの葉から分離した植物乳酸菌の働きが鍵に。パイナップル果汁で培養し、カプセル剤に加工。これを摂取したマウスが劇的に改善した。
「炎症性腸疾患の患者数は推定で国内に29万人、米国ではその5倍といわれる。治療が難しく、患者を苦しめてきたが、治る可能性のあることが確認できた」
02年春、中国醸造(現サクラオB&D)に勤める教え子からの相談が端緒になった。酒かすのヘルスケア機能性の証明を契機に、植物乳酸菌の研究開発と社会実装は20年以上に及ぶ。野村乳業や広島駅弁当、フジスコなどの県内企業含め20社内外が新商品開発に挑み、市場開拓につなげている。この間に健康志向が年々高まり、追い風になった。カインズ(岐阜)は、サクラオB&Dがパウダー化した植物乳酸菌を使って飲料や酒、ガム、マウスウォッシュ、ペットフードなどとPB展開を広げている。
「小学生の頃に読んだ科学者パスツールの伝記に感銘した。発酵現象や微生物が感染症の原因であると明らかにしただけでなく、その予防と治療法開発に生涯をささげた生き方が道しるべとなった」
高度経済成長の代償で公害問題が顕在化した日本の現状に衝撃を受け、化学より生物学的色彩の濃い学問を追究しようと発酵工学を選択した。
教授に就く41歳を前に日仏科学協力事業の交換研究者としてパリへ。パスツール研究所で抗がん剤ブレオマイシンをつくる微生物(放線菌)の自己耐性機構解明に挑んだ。
長寿大国、日本は健康寿命の延伸が大きな命題。腸内環境が〝元気で長生き〟の源泉といわれる。病原菌やウイルスがすみにくい環境をつくる上で、腸まで生きて届く野菜や果物などの植物由来の乳酸菌は大きな可能性を秘める。
野村乳業の植物乳酸菌飲料との出会いが契機になり、半導体製造装置製作などの実績も多数ある旭興産グループ(東京)は自社農園で薬草栽培などを手掛けるほか、微生物のゲノム解析を容易にする装置や薬草の養液栽培装置を開発し、杉山研究室に納入した。杉山教授は創薬も視野に広島発の植物乳酸菌で世界の人々を健康にする志を抱く。
長崎大熱帯医学研究所の医師、柴田紘一郎がケニアで献身的な医療活動に従事したエピソードに触発され、さだまさしは「風に立つライオン」を作詞、作曲。信念に従い、困難にもひるむことなく走り続ける姿に思いをはせる。
昨年12月刊行した杉山教授の著作「科学者があれこれ好奇心で和歌をよむ」の隅々にその探究心があふれている。微生物の専門知識を駆使したミステリー小説にも挑もうとしている。著作「植物乳酸菌の挑戦」や、伝統と革新の微生物利用技術を表した「発酵」からも研究者の道を究める情熱が伝わってくる。